VOCALOID 第2世代(インターネット文化)
VOCALOID 第2世代(インターネット文化)
概要
発祥:2008年 日本
「メルトショック」を経てVOCALOIDの知名度が急速に高まると、技術力の高いクリエイターが続々とコミュニティに参加するようになった。2009年以降、ニコニコ動画に投稿されるVOCALOID楽曲には高度なアニメーションを伴う作品が増え、楽曲の完成度も商業作品に匹敵するレベルへと進化していった。
全盛期:2010年〜2012年 日本
2010年代前半には、美麗なアニメーションを付加した楽曲動画が流行し、コンポーザー・イラストレーター・動画編集者など複数人による制作体制が確立された。このチーム制作の登場は、「誰でも制作・発表・評価できる」ことを前提としていた初期のVOCALOIDシーンに変化をもたらし、とりわけ精鋭ボカロPが人気を集める結果となった。
第2世代のコンポーザーは、第1世代と異なり「VOCALOIDをひとりのキャラクター」としてではなく、「楽曲制作のためのツール」として捉える傾向が強かった。そのため、第1世代に多く見られた製品由来のキャラクター性やテーマ性は薄れ、代わりにコンポーザー自身の音楽的魅力によって支持を得るケースが増加した。
衰退:2012年
VOCALOID文化は多様な要素を取り込みつつ商業化・大衆化(第3世代)へと移行し、第2世代は徐々に勢いを失っていった。
影響を受けたジャンル
第2世代が発展していくとともに Concepted VOCALOID も発展していき、双方共に影響しあった。
音楽的特徴
楽式
第1世代のsupercellによる『くるくるまーくのすごいやつ』(2009年)や、wowakaが発表した多くの楽曲では、「リフ | A | リフ | A | B | C」という特徴的な楽式が用いられていた。この構造は第2世代以降の多くの楽曲に影響を与えている。
※本サイトでは便宜上「wowaka式」と呼称する。
VOCALOIDでの例
- supercell – くるくるまーくのすごいやつ (2009.3.4)
- wowaka – 裏表ラバーズ (2009.8.30)
- wowaka – ローリンガール (2010.2.14)
- wowaka – ワールズエンド・ダンスホール (2010.5.18)
- DECO*27 – モザイクロール (2010.7.15)
- ハチ – マトリョシカ (2010.8.19)
- YM – 十面相 (2011.1.14)
- ハチ – パンダヒーロー (2011.1.23)
- じん(自然の敵P)– 透明アンサー (2012.2.5)
- Last Note. – セツナトリップ (2012.5.3)
- れるりり – 脳漿炸裂ガール (2012.10.19)
- じん(自然の敵P)– 夜咄ディセイブ (2013.2.17)
- Neru – ロストワンの号哭 (2013.3.4)
- 日向電工 – ブリキノダンス (2013.3.10)
- れるりり – 一触即発☆禅ガール (2013.7.12)
- じん(自然の敵P)– サマータイムレコード (2013.9.2)
- れるりり – 猪突猛進ガール (2013.11.8)
- n-buna – 夜明けと蛍 (2014.11.11)
- れるりり – 厨病激発ボーイ (2015.1.2)
- Orangestar – Trash Day (2017.1.18)
- kemu – 拝啓ドッペルゲンガー (2017.5.31)
- Orangestar – Henceforth (2020.5.21)
VOCALOID楽曲以外での例
- Whitesnake – Still of the Night (1987.3.23)
- can/goo – まぼろし (2002.11.22)
- ASIAN KUNG-FU GENERATION – リライト (2004.8.4)
- MELL – Red fraction (2006.6.14)
- ONE OK ROCK – 内秘心書 (2007.4.25)
- DOES – 修羅 (2007.5.16)
- 泉こなた(平野綾),柊かがみ(加藤英美里),柊つかさ(福原香織),高良みゆき(遠藤綾) – もってけ!セーラーふく (2007.5.23)
- Kalafina – oblivious (2008.1.23)
- 川田まみ – PSI-missing (2008.10.29)
- 風浦可符香, 木津千里, 木村カエレ, 関内・マリア・太郎, 日塔奈美 & 大槻ケンヂと絶望少女達 – 林檎もぎれビーム! (2009.7.22)
- スキマスイッチ – ゴールデンタイムラバー (2009.10.14)
- 川田まみ – No buts! (2010.11.3)
- FictionJunction – stone cold (2011.8.3)
- BUMP OF CHICKEN – 記念撮影 (2019.7.10)
- Fear, and Loathing in Las Vegas – Burn the Disco Floor with Your ”2-step”!! (2019.11)
- 米津玄師 – ひまわり (2020.8.5)
- Fear, and Loathing in Las Vegas – Gratitude (2020.9.30)
- ヤングスキニー – ベランダ feat. 戦慄かなの (2024.2.14)
- キタニタツヤ – ずうっといっしょ! (2024.5.14)
その他
楽器
- メインボーカルにはVOCALOIDを起用。
クリプトン・フューチャー・メディア社以外のVOCALOID製品が増え、とくにインターネット社の「Megpoid(GUMI)」や1st PLACE社の「IA -ARIA ON THE PLANETES-」が新たに採用された。 - 第1世代と比較すると生演奏楽器の使用が増えたが、J-POP全般と比べると電子楽器やソフト音源の比率は依然として高い。
歌詞
- VOCALOIDのキャラクター性を前面に押し出したり、キャラクター自身の心情を歌う作品は少ない。一方で、ボカロP独自の世界観を強く打ち出す楽曲が多く制作された。
精神性
- 動画タイトルには「オリジナル曲PV」と明記されることが多い。
- 動画内ではVOCALOIDキャラクターがイメージ作りの要素として登場するが、楽曲の内容と直接的な関連性は持たない場合が多い。
代表曲
小林オニキス – 【初音ミク】 サイハテ 【アニメ風PV・オリジナル曲】(2008.1.16)
『サイハテ』は、初音ミク発売からわずか4か月後に発表されたVOCALOID黎明期の代表作であり、当時としては極めて珍しい本格的なアニメーションPVを伴う作品として知られる。2008年初頭のニコニコ動画では、VOCALOID楽曲の多くが1枚絵や簡易スライドショーを背景に用いた形式であり、動きのある映像は稀であった。本作はフルアニメーションによるビジュアルと楽曲の融合を実現し、視覚と聴覚を一体化させた表現の先駆けとして高く評価された。
『サイハテ』は、その後のVOCALOIDシーンにおける「映像と音楽の同時創作」や「PV付きオリジナル曲」という制作スタイルを広めるきっかけとなり、アート性・世界観の構築を重視する作家層の登場を促した。
iroha(sasaki) – 【鏡音リン】炉心融解【オリジナル】(2008.12.20)
『炉心融解』は、コンポーザーのiroha(sasaki)、作詞家のkuma(alfled)、イラストレーターの三輪士郎と裏花火、動画クリエイターのなぎみそという5人による合作で制作された、初期VOCALOID文化を象徴する一曲である。ボーカリストには鏡音リンを起用し、2024年現在、ニコニコ動画において鏡音リン単体のオリジナル曲として最も多く再生された作品であり、VOCALOID全体でも20番目という高い再生数を誇る(ただし、動画削除の経歴があり正確な累計値は不明)。
2009年11月9日にはJOYSOUND週間ランキングで1位を獲得し、しかも公共放送では扱われない過激なテーマを持つ曲として初の快挙を成し遂げた。この出来事は、VOCALOIDがインターネット上のオタク文化という枠を越え、カラオケを介して一般的な若者文化に浸透していく転換点の一つとなった。また、楽曲の映像・音楽・キャラクター表現が高度に統合された事例として、後のボカロ作品制作における「チーム制作」モデルの先駆けとしても影響を与えている。
アゴアニキ – 【巡音ルカ】ダブルラリアット【オリジナル】(2009.2.5)
『ダブルラリアット』は、アゴアニキによる作曲・制作で、クリプトン・フューチャー・メディア社の巡音ルカをボーカルに起用した代表的VOCALOID楽曲である。2024年現在、ニコニコ動画における巡音ルカ単体のオリジナル曲として最多再生数を誇り、VOCALOID全体でも33番目に位置する高い人気を維持している。
映像面では、swf形式のインタラクティブ性を活かし、視聴者が一見しただけでは気付けない複数の隠しギミックが盛り込まれており、リプレイ性と話題性を大きく高めた。公開からわずか30日でミリオン再生を達成し、この速度は『みくみくにしてあげる♪』の25日に次ぐ当時2番目の記録となった。こうした要素は、楽曲の音楽性だけでなく映像・演出面でも初期VOCALOID文化における「参加型コンテンツ」的な広がりを示し、後続のクリエイターたちに動画演出の新たな方向性を提示する契機となった。
DECO*27 – 【GUMI】モザイクロール【オリジナル曲PV付】(2010.7.15)
『モザイクロール』は、当時既に人気を確立していたコンポーザーDECO*27が、イラストレーターakkaとmirtoと共に制作したコラボレーション作品である。ボーカルにはMegpoid(GUMI)を起用し、2010年夏の公開直後からニコニコ動画を中心に爆発的な再生数を記録。2024年現在、GUMI単体のオリジナル曲としては史上最多の再生数を誇り、全VOCALOID楽曲の中でも6位に位置する。公開後30日以内にミリオンを達成したことで、当時のGUMI人気を一気に押し上げる原動力となった。
また、『モザイクロール』はConcepted VOCALOIDと呼ばれるコンセプト連作の潮流に影響を与え、DECO*27自身も『二息歩行』『弱虫モンブラン』など、物語性や感情の連続性を感じさせる楽曲群を制作。これにより、単発的ヒットではなく“楽曲世界観全体”を消費するリスニング文化を形成し、第3世代・第4世代のボカロPにも大きなインスピレーションを与えた。
ハチ – 【オリジナル曲PV】マトリョシカ【初音ミク・GUMI】(2010.8.19)
ハチ – 【オリジナル曲PV】 パンダヒーロー 【GUMI】(2011.1.23)
ハチは、当時のVOCALOIDシーンにおいて主流であった「初音ミクやGUMI=アイドル的ポップス」という固定観念から逸脱し、ダークでホラー的な世界観を前面に押し出す作風で頭角を現したクリエイターである。初期には『結ンデ開イテ羅刹ト骸』や『Mrs.Pumpkinの滑稽な夢』、『リンネ』などで多様な音楽スタイルを試しつつ、物語性と不気味さを融合させた表現を模索していた。
- 結ンデ開イテ羅刹ト骸 (2009.7.6)
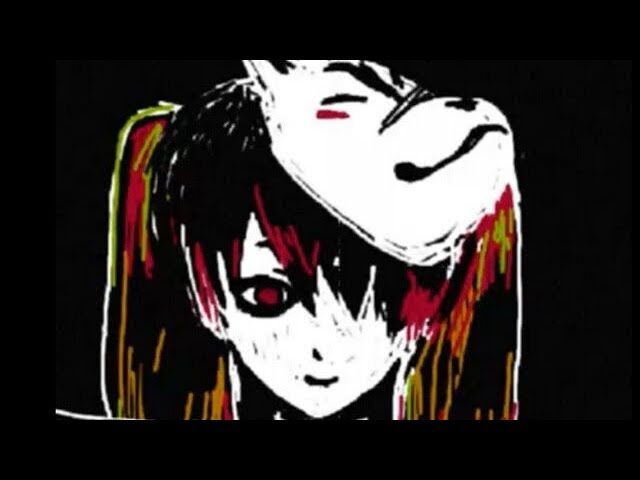
- Mrs.Pumpkinの滑稽な夢 (2009.10.12)

- リンネ (2010.7.21)

その集大成ともいえる『マトリョシカ』では、初音ミクとGUMIを起用し、狂騒的なリズムと無国籍感漂うメロディ、意味を攪拌したような歌詞によって、視聴者の強烈な印象を獲得。続く『パンダヒーロー』では、ロック調の疾走感と犯罪譚的な歌詞が融合し、GUMIの声質を活かした荒々しい世界観を確立した。両作とも印象的な手描き風PVが楽曲世界を補完し、音楽と映像の一体感による没入感を強めた。
2024年現在、『マトリョシカ』はニコニコ動画におけるVOCALOID楽曲で5番目、『パンダヒーロー』は28番目の再生数を誇り、いずれもダブルミリオンを達成。これによりハチは、ryo・wowakaに次いで史上3人目となる2曲のダブルミリオン達成者となり、かつ未成年での達成は唯一という偉業を成し遂げた。この成果は、VOCALOID文化における表現の幅を拡張し、「VOCALOIDのキャラクターソング」という枠を超えた芸術的作品制作の可能性を広く提示した。
164 – 天ノ弱/164 feat.GUMI (2011.5.28)
『天ノ弱』は、コンポーザー164が制作し、ボーカリストにGUMIを起用した楽曲である。メタルコアやデスメタルに由来する「ATG型」(At The Gates型)のギターリフが特徴で、疾走感と重厚感を兼ね備えたサウンドは、それまでのVOCALOID楽曲の主流だったエレクトロポップ路線とは一線を画した。この楽曲は、同時期のDECO*27『モザイクロール』と並び、「VOCAROCK」と呼ばれるJ-Rock寄りの新ジャンルを確立する契機となり、バンドサウンドとVOCALOIDの融合に対するリスナーとクリエイター双方の認識を大きく変えた。
2024年現在、『天ノ弱』はニコニコ動画においてGUMI単体のオリジナル曲として2番目に多い再生数を誇り、VOCALOID全体でも14番目に位置している。ロックバンドによるカバーやライブ演奏の機会も多く、VOCALOID曲がバンドシーンへ浸透するきっかけを作った歴史的作品として、その影響力は10年以上経った現在も色褪せていない。
黒うさP – 『初音ミク』千本桜『オリジナル曲PV』(2011.9.17)
『千本桜』は、コンポーザー黒うさP、イラストレーター一斗まる、動画クリエイター三重の人、ギタリストhajimeの4名による合作で制作された、VOCALOID史において象徴的な楽曲である。和楽器とロックサウンドを融合させた疾走感のあるアレンジと、大正浪漫を思わせる世界観、社会風刺を含んだ歌詞が特徴で、初音ミクの力強い歌唱と鮮烈なビジュアルが相まって爆発的な人気を博した。
2024年現在、ニコニコ動画においてVOCALOID楽曲として歴代最多再生数を誇る作品であり、発表から10年以上経た今もその記録は揺るがない。J-Popアーティストによる公式・非公式カバーも多数生まれ、JOYSOUND総合カラオケランキングでは2012年度から2014年度にかけて3年連続で3位を記録。これはVOCALOID楽曲として異例の国民的浸透度を示すものであり、ボカロ文化を一般大衆層にまで押し広げた決定的な契機となった。
さらに、メディアミックス展開も盛んで、小説化・漫画化に加え、ミュージカルや歌舞伎などの舞台芸術にも進出。2013年にはピアニストまらしぃによるピアノアレンジ版がトヨタのCMソングに採用されるなど、VOCALOID楽曲が産業広告や伝統芸能の領域にまで進出した先例としても重要である。その文化的波及力は、インターネット発の音楽コンテンツがいかにして社会的認知を獲得し得るかを示す象徴的事例となった。
kemu – 六兆年と一夜物語 (2012.4.11)
『六兆年と一夜物語』は、コンポーザーkemuとスズム、イラストレーターのハツ子、動画クリエイターのke-sanβによる4人の合作で制作された、IAをボーカリストに起用した代表的VOCALOID楽曲である。発表当時、IAは2012年1月に発売されたばかりの新しいVOCALOIDであり、本作はその声質の魅力を広く知らしめる役割を果たした。
2024年現在、『六兆年と一夜物語』はニコニコ動画におけるIA単体のオリジナル曲として2番目に多い再生数を誇り、VOCALOID全体でも12番目に位置する人気を維持している。
Neru – 【鏡音リン】 ロストワンの号哭 【オリジナルPV付】(2013.3.4)
『ロストワンの号哭』は、コンポーザーNeru、友達募集P、イラストレーター456による合作で制作された、鏡音リンをボーカリストに起用したVOCALOID楽曲である。映像では456による鋭利で印象的なキャラクターデザインと、文字演出を駆使したPVが楽曲の自己否定感の感情的爆発を視覚的にも表現している。
2024年現在、『ロストワンの号哭』はニコニコ動画において鏡音リン単体のオリジナル曲として2番目に多い再生数を誇り、VOCALOID全体でも25番目の再生数を記録。
n-buna -【初音ミク】 ウミユリ海底譚 【オリジナル曲】(2014.2.24)
『ウミユリ海底譚』は、透明感のあるコード進行と浮遊感を持ったメロディ、そして幻想的な海底世界を描く詩的な歌詞が特徴で、聴き手を没入させる独特の叙情性を備えている。サビで一気に開放される旋律と、淡い郷愁を呼び起こす情景描写は、n-bunaの作風を象徴する要素としてその後の活動にも色濃く反映された。ニコニコ動画におけるVOCALOID楽曲全体で18番目に多い再生数を記録しており、発表から10年経った今も根強い人気を誇る。
本作の成功を経て、n-bunaはロックバンド的編成と女性ボーカルsuisを迎えた音楽ユニット「ヨルシカ」を結成。YouTubeに投稿された複数のMVが1億回再生を超えるなど、日本の音楽シーンを代表する存在となり、インターネット発アーティストがメジャーシーンへ進出する流れを象徴する事例ともなった。
40mP -【初音ミク】恋愛裁判【オリジナルMV】(2014.6.10)
『恋愛裁判』は、コンポーザー40mPを中心に、編曲・アニメーション・イラストなど計7名のクリエイターが関わって制作された楽曲である。映像面ではカラフルでテンポ感のあるアニメーションが用いられ、楽曲の明るさと物語性を視覚的にも強化した。
本作はニコニコ動画よりもYouTubeを主戦場として人気を拡大し、国内外の視聴者から支持を得たことで、後のボカロPによるYouTube発信戦略にも影響を与えた点でも特筆される。当時、VOCALOID楽曲のヒットはニコニコ動画主導が主流であったが、『恋愛裁判』はYouTubeでの拡散と海外ファン層の獲得に成功し、ボカロ文化のグローバル化を象徴する事例となった。
Kikuo – 愛して愛して愛して (2015.3.6)
『愛して愛して愛して』は、Kikuoが制作した、初音ミクをボーカルに起用したダークで中毒性の高いVOCALOID楽曲である。耳に残る高音域の旋律と反復的で催眠的なサウンド構造、そして狂気と依存をテーマにした歌詞が特徴で、聴く者に強烈な印象を与える。独特な不安感と美しさを併せ持つKikuo特有の音楽性が全面に押し出され、国内外のリスナーからカルト的な支持を獲得した。
本作はYouTubeにおけるVOCALOID楽曲の中で3番目に多い再生数を誇り、その人気はニコニコ動画中心だったVOCALOID文化の主戦場をYouTubeへと大きく移行させる契機の一つとなった。特に、従来のオタク層だけでなく、一般リスナー層や海外の視聴者層にも浸透し、VOCALOID楽曲の消費構造に変化をもたらした。
このメガヒットは、第2世代(ニコニコ動画全盛期を支えたVOCALOIDシーン)の衰退と、第3世代(YouTubeを主舞台とした国際的な広がり)の興隆を象徴する出来事ともいえる。以降、YouTubeでの視聴・拡散を前提とした楽曲制作やプロモーション戦略が主流化し、ボカロシーンの世代交代を決定付けた歴史的作品となった。
Neru – [MV] 脱法ロック / Neru feat. 鏡音レン (2016.06.19)
『脱法ロック』は、コンポーザーNeru、イラストレーターりゅうせー、そしてコーラスに東京非リアフィルハーモニー所属メンバーを含む計9名によって制作された、鏡音レンをボーカルに起用したVOCALOID楽曲である。軽快かつ疾走感のあるバンドサウンドに、皮肉と社会風刺を織り交ぜた歌詞を乗せた構成が特徴で、キャッチーなメロディと中毒性の高いリズムが強い印象を残す。
2024年現在、『脱法ロック』はニコニコ動画における鏡音レン単体のオリジナル曲として最多再生数を誇り、レンの代表曲として不動の地位を確立。本作は、第2世代(ニコニコ動画全盛期)後半の人気が緩やかに衰退していく時期に発表されたが、第4世代を象徴する『ゴーストルール』(DECO*27)、『エイリアンエイリアン』(ナユタン星人)、『チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!』(和田たけあき)といったヒット曲と時期的に呼応し合い、VOCALOIDシーンの再活性化に貢献した。
ハチ – ハチ MV「砂の惑星 feat.初音ミク」(2017.7.21)
『砂の惑星』は、ハチが5年3ヶ月ぶりに発表した楽曲で、初音ミクの創作文化を体感できる複合型イベント「マジカルミライ2017」のテーマソングとして制作された。楽曲の世界観は、砂漠化した惑星として象徴的に描かれるニコニコ動画やVOCALOIDシーンを舞台に、衰退や世代交代をテーマに据えたと解釈されることが多く、過去の栄光と新しい時代への移行が複雑に交錯するメッセージ性を持っている。
発表直後から圧倒的な注目を集め、デイリーランキングで10万回再生を8日連続記録。さらに、わずか6日で100万回再生を達成し、当時最速記録だった『FREELY TOMORROW』(2011年)の20日を大幅に更新した。その後も勢いを保ち、『千本桜』(2011年)以来となる1年以内の400万回再生を記録し、第2世代のVOCALOIDリバイバルを象徴する楽曲となった。
2022年には1000万回再生を達成し、ハチはDECO*27に次ぐ史上2人目の「同一Pによる2曲テンミリオン」達成者となった。2024年現在、『砂の惑星』はニコニコ動画でVOCALOID楽曲の中で11番目、YouTubeでは5番目に多い再生数を誇り、ネット音楽史における両プラットフォームをまたいだヒットの代表例となっている。その存在は、ボカロ文化の過去と現在、そして未来を繋ぐ象徴的な楽曲として位置付けられる。
Giga – ‘劣等上等'(BRING IT ON) ft.鏡音リン・レン【MV】(2018.7.13)
『劣等上等』は、Gigaが制作したマジカルミライ「鏡音リン・レン10th Anniversary」のテーマソングであり、エネルギッシュなエレクトロサウンドと攻撃的なラップパートが融合した一曲である。映像は鮮やかなカラーリングと躍動感のあるモーションを特徴とし、楽曲の熱量や挑戦的なムードを視覚的にも増幅している。
2024年現在、『劣等上等』はYouTubeにおける鏡音レンが起用されたオリジナル曲として最多再生数を誇り、リン・レンの周年記念曲としては異例のロングヒットとなっている。タイアップ曲としての役割を超え、現代的なEDM/VOCALOIDクロスオーバーの成功例として、後続のアップテンポ系ボカロ曲の制作指針にも影響を与えた。