VOCALOID 第1世代(黎明期)
VOCALOID 第1世代(黎明期)
概要
発祥:2000年代 日本
全盛期:2007年〜2010年
2003年、ヤマハ株式会社が音声合成ソフトウェア「VOCALOID」を発表。翌2004年には、イギリスのZERO-G社から「LEON」「LOLA」、日本のクリプトン・フューチャー・メディア株式会社から「MEIKO」など、初期を代表する製品が発売された。しかし、これらはいずれも商業的な成功には至らなかった。
転機となったのは2007年8月31日、クリプトン・フューチャー・メディアから発売された「初音ミク」である。本来は音楽制作ツールの一つに過ぎなかった合成音声に、明確なキャラクター性を付与し「バーチャルアイドル歌手」として位置づけたことで、従来の音楽制作者層だけでなくオタク層にも広く受け入れられた。この戦略は、動画投稿プラットフォーム「ニコニコ動画」を中心とする爆発的な人気へとつながった。
2010年代前半になると、アンダーグラウンドなオタク文化としてのVOCALOIDは次第に衰退していった。一方で、VOCALOIDは新たな自己表現の手段として幅広いクリエイターに利用されるようになり、その文化は形を変えて継続した。そして2016年、『ゴーストルール』のヒットを契機に、第1世代の精神性を色濃く受け継いだ第4世代が台頭することとなった。
影響を受けたジャンル
- J-Pop
- Idol
VOCALOID第1世代の精神性は、日本のアイドル文化に影響を受けた育成シミュレーションゲーム『THE IDOLM@STER』(以下、アイマス)に由来する。アイマスでは、プレイヤーが女性アイドルのプロデューサーとなり、彼女たちをトップアイドルへと成長させることが目的となっている。この「アイドルをプロデュースする」という精神性が、そのまま初音ミクを“プロデュース”するという文化の誕生につながった。
アイマスは、初音ミクが発売された2007年当時、アーケード版およびXbox 360版の展開により一定のファン層を獲得しており、その文化圏の一部がニコニコ動画を通じてVOCALOIDコミュニティへ流入したことで、楽曲制作・キャラクター造形・ファン参加型の創作活動に強い影響を与えた。こうして、初音ミクを中心とした「プロデューサー的視点」でのファン文化が確立され、第1世代の特徴的な精神性として定着していった。
音楽的特徴・精神性
楽器
メインボーカリストにはVOCALOID(特にクリプトン・フューチャー・メディア社の製品)が多く起用された。制作予算の制約から、生演奏の楽器はほとんど用いられず、MIDIやSoundFont、SteinbergのVirtual Studio Technology Instruments(VSTi)、Audio Unit Instrumentsといったソフトウェア音源やサンプラーが主流であった。
歌詞
キャラクター性を前面に押し出し、キャラクター自身の心情を歌う楽曲が多く見られる。また、性的表現を含む作品も多い。
楽曲
オリジナル曲に加え、既存曲のカバーも多数制作され、コミュニティ内で盛んに共有・二次創作が行われた。
代表曲
Otomania – VOCALOID2 初音ミクに「Ievan Polkka」を歌わせてみた (2007.9.4)
2006年4月、フィンランドの伝統的ポルカ『Ievan Polkka』を用いたフラッシュアニメーション「ロイツマ・ガール」が世界的に流行し、その軽快なリズムとコミカルな演出はインターネットミームとして広く拡散された。その約1年半後、初音ミク発売からわずか4日後の2007年9月4日に、Otomaniaが「ロイツマ・ガール」をパロディ化した初音ミク歌唱版を発表。本作は、原曲のユーモラスな魅力と初音ミクのキャラクター性を掛け合わせたことで、「ニコニコ動画」を中心に瞬く間に人気を集めた。映像にはMikuMikuDance登場以前の手描きアニメーションが用いられ、当時の技術水準においても高い完成度を誇った。
この楽曲は、初音ミクを「キャラクター」として楽しむ文化の拡大に大きく寄与し、VOCALOIDと動画投稿サイトの相互発展を促す契機となった。特に、コミュニティがミーム的要素を取り込み再解釈していく流れは、その後の二次創作文化の礎となり、VOCALOIDシーンがインターネット文化と密接に結びついていく基盤を築いた歴史的作品である。
ika – 【初音ミク】みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 (2007.9.20)
『みくみくにしてあげる♪』は、初音ミク登場初期を代表するオリジナル曲であり、ファンの間では「神話」と称される存在となった。2024年現在、ニコニコ動画におけるVOCALOID楽曲の中で再生数第2位を記録している。
初音ミク発売から約1か月後、コミュニティでは単に歌を歌わせるだけでなく、そのためのオリジナル曲制作、3Dモデルの作成、モデルに合わせたダンスモーションの付与、衣装やイラストの制作など、多方面から作品世界を構築する活動が活発化した。こうした一連の行為は、まるで初音ミクという“アイドル”をプロデュースしているかのように見え、その担い手たちは次第に「ボーカロイド・プロデューサー(ボカロP)」と呼ばれるようになった。
本作はその象徴的存在であり、シンプルながらも耳に残るメロディと、初音ミクのキャラクター性を全面に押し出した歌詞・演出が相まって、後続のファン参加型創作文化の原点となった。インターネット黎明期における二次創作と音楽制作の融合を示す歴史的楽曲として、現在も高い評価を受け続けている。
kobapie – 「卑怯戦隊うろたんだー」をKAITO,MEIKO,初音ミクにry【オリジナル】修正版 (2007.11.28)
『卑怯戦隊うろたんだー』は、初音ミクに加え、クリプトン・フューチャー・メディア社の初期VOCALOID製品である「MEIKO」と「KAITO」をボーカリストに起用した、黎明期を代表する多キャラクター参加型オリジナル曲である。2024年現在、ニコニコ動画におけるMEIKOとKAITOを起用したオリジナル曲としては、最も多くの再生数を誇っている。複数のVOCALOIDを同時に主役として扱う発想は、当時としては新鮮であり、キャラクター間の関係性や役割を物語的に描く手法の先駆けとなった。
ryo – 初音ミク が オリジナル曲を歌ってくれたよ「メルト」 (2007.12.7)
ryo – 初音ミク が オリジナル曲を歌ってくれたよ「ワールドイズマイン」(2008.5.31)
ryo – 初音ミクがオリジナルを歌ってくれたよ「ブラック★ロックシューター」(2008.6.13)
supercell – supercell (2008.8)
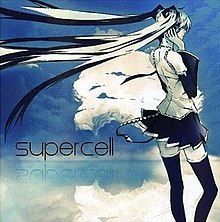
コンポーザーryoによる一連の楽曲は、『みくみくにしてあげる♪』のようにキャラクター性を前面に押し出す路線とは異なり、J-Pop的なメロディとアレンジを積極的に取り入れた点が特徴である。特に『メルト』は、当時派遣社員だったryoが制作し、「1万5000円で誰でも初音ミクを思い通りに歌わせられる」という事実を世間に印象づけた。このインパクトはVOCALOIDに関心のなかった層にも届き、第2世代ボカロPの誕生と拡大に大きな影響を与えた。2024年現在、同曲はニコニコ動画におけるVOCALOID楽曲再生数ランキングで第3位に位置している。
また、公開当時には「メルトショック」と呼ばれる現象が発生。ニコニコ動画のマイリスト登録ランキングが『メルト』関連動画で埋め尽くされるほどの反響を呼び、当時の初音ミク人気の絶頂期を象徴する出来事となった。
その後、ryoはイラストレーター、デザイナー、ゲストボーカルなど多彩なメンバーを集め、制作集団「supercell」を結成。2008年8月に発売された1stアルバム『supercell』は、現在でもVOCALOID関連CDとして史上最高の売上を誇る。アルバムに収録されている『ワールドイズマイン』は再生数第17位、『ブラック★ロックシューター』は第31位と、いずれも高い人気を維持している。
cosMo(暴走P) – 初音ミクオリジナル曲 「初音ミクの消失(LONG VERSION)」(2008.4.8)
『初音ミクの消失(LONG VERSION)』は、BPM240という極端な高速テンポに乗せて畳みかける膨大な歌詞量が特徴の楽曲であり、人間による歌唱は事実上不可能とされる。こうした「機械だからこそ可能な歌唱表現」を最大限に活用することで、VOCALOIDという音声合成ソフトの特性を鮮烈に提示した作品である。
歌詞・テーマは初音ミクのキャラクター性を直接的に題材とし、存在の消失と再生を描く物語構造が盛り込まれている。その結果、本作は「初音ミクのために作られた歌」の象徴的存在として広く認知され、ファンや制作者に強い印象を残した。
技術的にも、当時の調声技術やシーケンスの精緻さは群を抜いており、VOCALOIDを使った楽曲制作における一つの到達点とされる。2017年時点で、ニコニコ動画におけるVOCALOID楽曲再生数ランキングで第13位に位置しており、長期にわたり高い人気と評価を維持している。
doriko – 「ロミオとシンデレラ」 オリジナル曲 vo.初音ミク (2009.4.6)
doriko – ロミオとシンデレラ (2010.11)

『ロミオとシンデレラ』は、当時アンダーグラウンドで支持を得ていた性的表現を、大衆に受け入れられるポップス的な楽曲構造へと昇華させたことで高い人気を獲得した作品である。疾走感のあるバンドサウンドに、恋愛の衝動と禁忌を織り交ぜた歌詞を乗せることで、キャッチーさと背徳感を同時に表現している。このアプローチは、過激さよりも情緒性とドラマ性を重視する方向へとVOCALOID楽曲の表現幅を広げ、第1世代の音楽性の成熟を象徴する一例となった。2024年現在、本作はニコニコ動画におけるVOCALOID楽曲再生数ランキングで第21位を記録している。
また、2010年にリリースされたdorikoの2ndアルバム『ロミオとシンデレラ』は、VOCALOID関連CDとして初めてハイレゾ音源でのダウンロード配信に対応した作品としても知られ、音質面における新たな試みを先駆けた歴史的意義を持つ。
wowaka – 初音ミク オリジナル曲 「裏表ラバーズ」(2009.8.30)
wowaka – 初音ミク オリジナル曲 「ローリンガール」(2010.2.14)
wowaka – 初音ミク・巡音ルカ オリジナル曲 「ワールズエンド・ダンスホール」(2010.5.18)
『裏表ラバーズ』は、『初音ミクの消失』に代表される機械的かつ超高速なボーカル表現と、『ロミオとシンデレラ』に見られる性的テーマを融合させた楽曲であり、黎明期のボカロ文化を象徴する作品である。2024年現在、ニコニコ動画におけるVOCALOID楽曲再生数ランキングで第19位を記録している。
2023年には、『ローリンガール』と『ワールズエンド・ダンスホール』がそれぞれ1000万回再生を突破し、DECO*27、ハチ(米津玄師)に次いで史上3人目となる「同一Pによる2曲テンミリオン」を達成。さらに同年、『裏表ラバーズ』も1000万回再生を達成し、史上初の「同一Pによる3曲テンミリオン」という快挙を成し遂げた。
wowakaの楽曲は、イントロのリフをAメロ後に再現する独特の楽式構造を持ち、その時間芸術的な構造美は第2世代以降のアーティストに多大な影響を与えた。この手法は「ボカロらしさ」と呼ばれる音楽性の確立にも寄与し、VOCALOID音楽の作曲アプローチにおける重要な指標となっている。
Mitchie M -【調教すげぇ】初音ミク『FREELY TOMORROW』(完成)【オリジナル】(2011.7.31)
『FREELY TOMORROW』は、その極めて精緻な調声技術によって、初音ミクの歌声を人間のボーカルに迫るほど自然かつ表情豊かに仕上げたことで話題となった作品である。
公開直後から爆発的な注目を集め、投稿からわずか10時間40分で10万回再生を達成。当時としては最速記録であり、その勢いのまま20日6時間4分後には100万回再生を突破した。この異例のスピードは、調声技術への驚きと共に、楽曲そのもののポップでキャッチーな魅力が幅広い層に受け入れられたことを示している。
本作はその後のVOCALOID楽曲制作において「人間らしい歌声を追求する」方向性を強く後押しし、技術的アプローチや調声研究の活性化にも大きく貢献した。
livetune – Tell Your World (2012.3)
『Tell Your World』は、Google ChromeのテレビCMソングとして制作され、日本国内にとどまっていたVOCALOID文化を世界へと広く知らしめる契機となった楽曲である。CM映像では、世界中のファンアートやメッセージが映し出され、初音ミクがグローバルな創作コミュニティの象徴として描かれた。このビジュアルと楽曲の組み合わせは、単なる広告の枠を超えた文化的メッセージとして高く評価された。
リリース後、iTunes Storeのダウンロードランキングで1位を獲得し、商業的にも大きな成功を収めた。本作は、VOCALOIDが日本のサブカルチャーから国際的なポップカルチャーへと飛躍するうえで欠かせないマイルストーンとなり、その後の海外展開やライブイベントの拡大にも影響を与えた。